
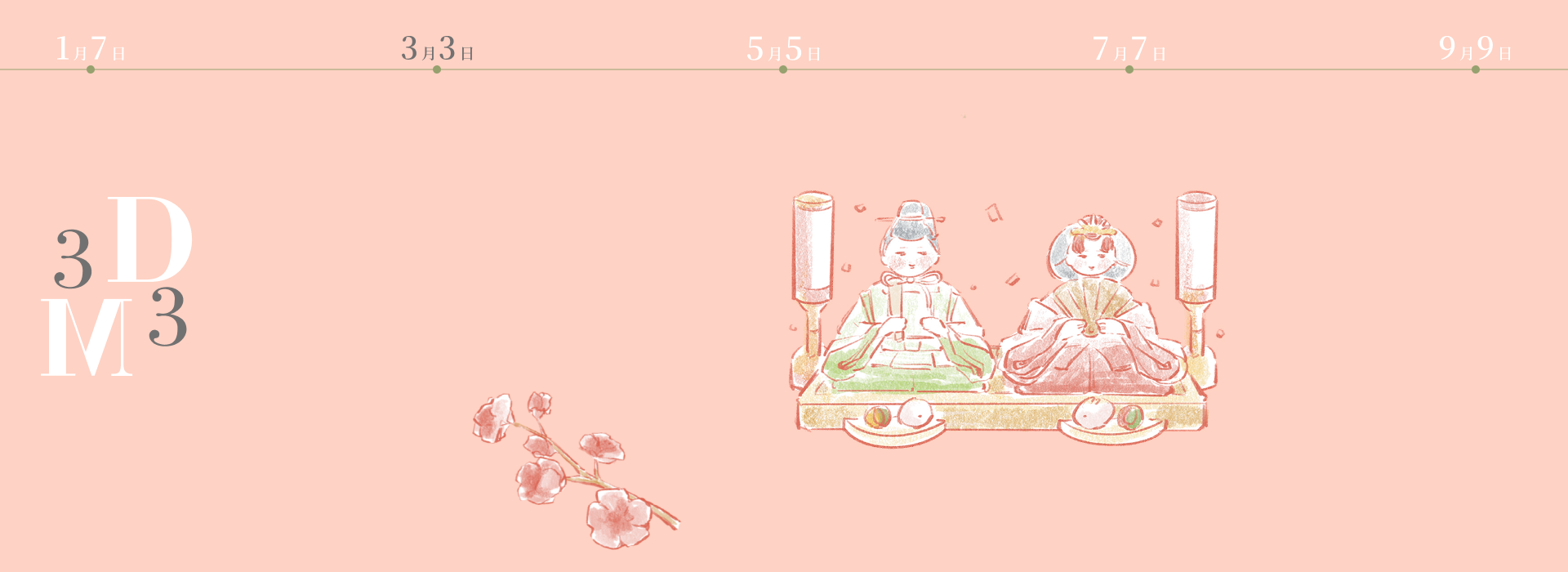
上巳の節句桃の節句

- 時代
- 平安時代~
- 由来
- 宮中では「曲水の宴」を張り、祓えをおこなっていた。 やがて、宴は廃り「流し雛」の風習となり、今の「雛まつり」に至る。
- 現在の行事
- 江戸時代以降より「雛まつり」として庶民の間に広まり女の子が生まれると、子供の身代わりの役目「お守り」として雛人形を飾るようになり、内裏雛や十五人揃いのひな壇に「雛の膳」※を供えたりする。
※「雛の膳」には桃酒・白酒・菱餅などを供える。何気ない供え物の中にも「娘の長命」を願う心が生きている。 - 本質
- 災厄をはらう。女の子の健やかな成長を願う。
- 季節の花
- 桃
-

雛人形
ひな人形には、生まれた子どもがすこやかで優しい女性に育つようにとの親の願いが込められています。
ひな人形をその子の形代と考えて、どうぞ災いがふりかかりませんように、また、美しく成長してよい結婚に恵まれ、人生の幸福を得られますようにという、あたたかい思いを込めて飾ります。



